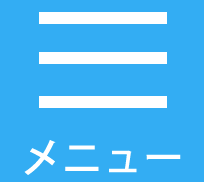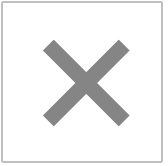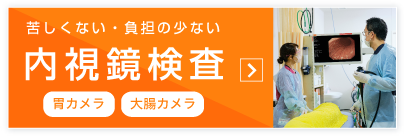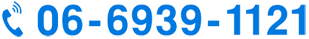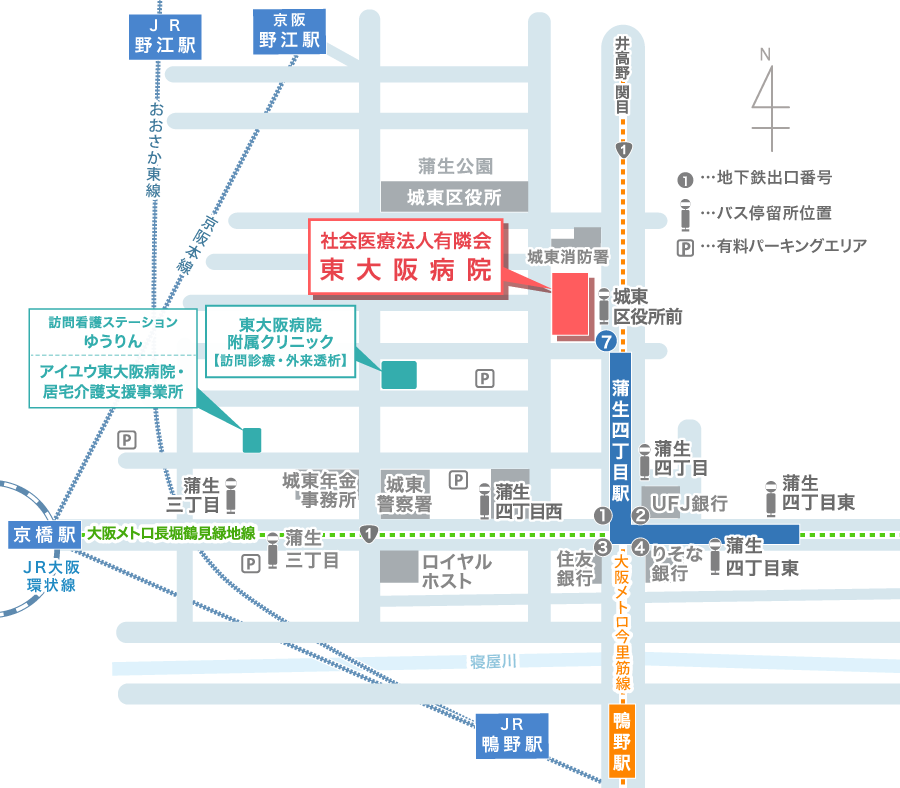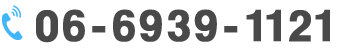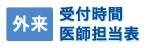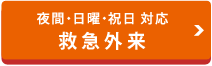透析に関すること
腎臓とは?(働き、代表的な腎臓疾患)
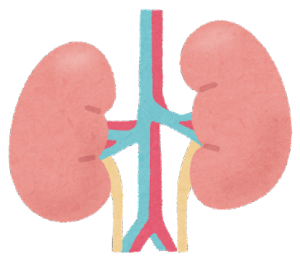
腎臓とは?
腎臓は尿をつくる器官で、腰よりやや高い位置の背中側に、背骨を挟んで左右1個ずつあります。ソラマメ型をした臓器です。一つが約150gほどです。
腎臓の働きとは?
腎臓には、体内の環境を最適な状態に整えるという大切な働き、カラダを常にバランスの取れた状態に維持する働きがあります。
腎臓は大きく分けると糸球体と尿細管に分けられます。糸球体には血液をろ過する働きがあります。
尿細管は糸球体でろ過されたろ液成分を調整する働きがあります。
アミノ酸やブドウ糖などの栄養素、ナトリウムやカリウム、リン、マグネシウムなどの様々なイオン(電解質)など必要なものまでろ過されないように、再吸収を行います。約99%が再吸収され、残り1%が尿になります。
腎臓は、尿量や体液の成分の濃度調節を行い、体液のバランスを一定に保ち、身体のむくみを防いだり、神経の伝達や筋肉の動きをスムーズにします。
腎臓は、血液(赤血球)を作るホルモンや、血圧を調整するホルモン、骨を丈夫にするホルモンなどを作ります。
<腎臓の主な機能>
・老廃物の排出
・体内水分量の調節
・電解質のバランス調整
・血液を作成するホルモンの分泌
・血圧の調整
・骨を強くするためのビタミンDの作成
代表的な腎臓の疾患
●糖尿病性腎症
糖尿病によって高血糖状態が持続し、腎臓の内部に張り巡らされている細小血管が障害を受けることで発症する。
悪化すると腎不全に移行し、血液透析などが必要となることもある。糖尿病性腎症の初期段階は自覚症状はない。
糖尿病性腎症の診断には、尿蛋白(アルブミン)や血中クレアチニンの測定が有効。
●慢性糸球体腎炎
糸球体に慢性的な炎症が起こり、血尿や蛋白尿を認める病気を総称して糸球体腎炎と呼ぶ。
慢性糸球体腎炎(慢性腎炎)は、血尿や蛋白尿が少なくとも1年以上持続するものをいう。
慢性糸球体腎炎には、IgA腎症、腹性腎症、紫斑病性腎炎などの疾患が含まれる。
●腎硬化症
高血圧が原因で腎臓の血管に動脈硬化を起こし、腎臓に障害をもたらす疾患。
●ネフローゼ症候群
尿に蛋白が大量に出てしまうために、血液中の蛋白が減り(低蛋白血症)、その結果、むくみが起こる疾患。
むくみは、低蛋白血症が起こるために血管の中の水分が減って血管の外に水分と塩分が増えるために起こる。
●腎不全
腎臓のろ過機能や再吸収機能が十分に働かなくなった状態。正常な時と比べて、腎臓の働きが30%以下になると腎不全という。
進行すると様々な自覚症状があらわれ、放っておくと血液透析や腹膜透析、腎臓移植などをしなければならなくなる。
【腎不全の症状】尿の異常(回数、量、色など)、動悸・息切れ、貧血、むくみ、高血圧、吐き気、発熱、頭や背中・腰・腹部の痛み、食欲不振、かゆみ
●急性腎不全
数日から数週間で腎不全になる。治療によって改善する可能性がある。
●慢性腎不全
数年かけてゆっくり腎不全になる。治療による改善は難しい。
●水腎症
病名ではなく、病態を表している。腎臓は、尿をつくる腎実質の部分とそれがたまる腎盂という部分に分かれている。尿は腎盂から尿管に移行して、膀胱にたまってきます。
膀胱が収縮することによって尿道から尿が出ますが、腎盂が膨れ上がって風船のように見える病態を水腎症という。
●多発性嚢胞腎
腎臓に嚢胞(水がたまった袋)がたくさんでき、腎臓の働きが徐々に低下していく、遺伝性の病気。
●腎結石
尿中のカルシウム成分などが結晶となり、これが集まって出来たもの。
普段は無症状であっても、結石が動くと、突然の激痛を引き起こす。
●腎腫瘍
腎臓に発生する腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍がある。良性腫瘍で頻度が高いのは腎血管筋脂肪腫、悪性腫瘍は成人に発生する腎細胞がんと小児に発生するウィルムス腫瘍が代表的。